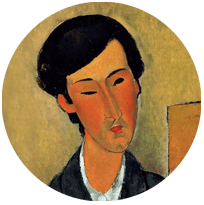『Diversified Investments』
画像抽出:DALL・E2
資産ポートフォリオを作る際の基礎、基本中の基本と言われる「分散」投資だが、世界標準といったような分散度合いの基準などは存在しない。
大手銀行等が推奨している基準といったものであればあるのかもしれないが、それにしたってその通りにしておけばいつ何時も大丈夫なんてことはあり得ない。それは断言できる。
あの有名なブリッジウォーターのレイ・ダリオ氏が個人投資家向けに推奨している「オール・シーズンズ戦略」なるものも、昨年(2022年)からの債券の暴落でかなり喰らうことになったようだ。
レイ・ダリオ氏の個人向けオール・シーズンズ戦略
株式(S&P 500等インデックス)…30%
中期米国債(7~10年満期)…15%
長期米国債(20~25年満期)…40%
金…7.5%
商品取引(コモディティ)…7.5%
というのがその内訳らしい。債券が全体の55%を占めているのが特徴と言えそうだが、これでは2022年はひとたまりもなかっただろう。
ただ自分はこのオール・シーズンズ戦略を批判している訳では全くない。むしろ逆で、債券の暴落が底を打った感のある今(2023年9月)、参考にすべきポートフォリオ割合なのかもしれない。
それに株式が30%に抑えられているのだから何とかショックには強いだろう。実際…
ITバブル崩壊の2002年、S&P 500が-22%程度だったところこのポートフォリオでは+7~8%程度
リーマンショックの2008年もS&P 500が-37%程度のところオール・シーズンズ戦略は-4%程度
だったという記述を目にした。理論値だとしても大したものである。
その他のポートフォリオ
参考までに上記以外のポートフォリオを見てみると、
株・社債・不動産(先進国、途上国、ドル建て、円建て、他通貨建て)… 40~60%
国債(米国・欧州)・現金 …10~30%
コモディティ(金、銀、プラチナ、ビットコイン、その他)…20~40%
といった、株式中心のものもあった。
これは最近YouTubeで人気(?)の高橋ダン氏のものだが、オール・シーズンズ戦略とは対照的に攻めている感じで、さすが元ウォール街のトレーダーといったところか。…知らんけど。
地合いが悪い場合は国債・現金比率を上げる、といった具合に、状況によってこれら3つの比率を変えるそうだ。
分散投資はリスクヘッジのため
表題の問いに戻ると、ではオール・シーズンズ戦略にならって5種類に分けると分散投資と言えるのかと考えてみると、何を組み込むかによるがとりあえずは分散投資というものには見える。少なくとも自分には。
では、分散投資をする理由はリスクヘッジだろうが、であれば5種類に分散したらリスクヘッジになるのか?という問いに対する答えは何を組み込むかによる、という前提の上で「その可能性がある」と言える程度に留まるしかない。
まずどういう種類のショックかで何の資産がどれくらい減るかは大分変ってくるだろうし、つまりくどいようだが何を保有しているか、その割合、またどこに住んでいるか等のその人の前提条件によっても答えは変わってくるはずだ。
リスクヘッジのための分散投資にはまず為替分散
「どこに住んでいるかによって…」と書いたのは例えば権威主義の国に住んでいる場合を念頭にしたものだが、住んでいるのが民主的で資本主義と呼ばれる国であれば、個人的にはまずは為替の分散を勧めたい。
2023年9月現在、留まるところを知らない勢いで円安が進行中だが、日本人だったら円だけでなく米ドルやユーロといった取引量の多い通貨でも銀行なり証券会社で投資用のアカウントを持っておき、何割かの資金をそれらにも振り分け投資していくべきだと思う。
自分の場合はザックリとユーロ50%、日本円40%、米ドル10%程度だ。他の投稿でも書いたが、円安がジワジワと進んできていた段階でなぜ米ドルと日本円の割合を入れ替えておかなかったのか、と後悔しきりである。…あるいはせめて20%程度に抑えられていれば少しは気持ちも違っただろうが。
更に、現状ではキャッシュ比率をかなり高くしているので日本円を持っているだけで日々かなり減価していっている感覚になるし、実際にしている。
投資先の銘柄選びは為替分散した後だ。
資産と時間を分散するのが分散投資
その上で、投資対象を分散する、カテゴリーから。上のオール・シーズンズ戦略のように株式、債券、コモディティ等に分け、更には日、米といった具合に国も一国に集中させない。自分の場合は更にクリプトも含める。
そして時間を分散、つまり毎月幾らずつ買っていく等の積立投資をする、というのが一般的によく言われる分散投資のやり方のようである。
そうなると分散のやり方、組み合わせ方はそれこそ無限と言って良いほどあることになる。
そして絶対にこれが正解といった明確な答えが無い中で投資先を決めていかなければならないが、でもだからこそ他人と比較する必要がない。どこの誰がどんなポートフォリオを組んでいようがどうでも良いことで、自分のが納得いくリターンを出し続けてくれさえすればそれで良いのだから。…と言ってもそれが簡単じゃないから他人のを見たりして勉強するのだけど。
国も必ず分散すべき
2023年9月現在まで、投資といえば大体がアメリカだ。株式時価総額でみればアップル1社で日本の75%に相当する規模なのだから、まぁ、どうしてもそうなりがちだ。
それにS&P500など米国の大型インデックスを見ても基本的には右肩あがりで、長期投資対象としてはやはり申し分ないと言えるだろう。
現に今流行り(?)のインデックス投資も主流は米株で、それは米国経済の将来性に賭けていることになる。
米国無双と言ってよい状況が続いているし今後も米国の経済成長は何だかんだ続いていくと自分も思っているが、それでも米国の一点張りは止めた方が良いと感じている。
自分のようなチャートを元にトレードするテクニカル派から見ても、バフェット指数で200%付近にいる米経済はさすがに危ういと思う。100%が平均水準なのだから、この指数だけで言えば米株は全体的に完全に割高で、理論上は今の半値が最適値ということになる。
S&P500が50%暴落する状況って想像するだけで恐ろしく、そしてトレーダーとしてはエキサイティングだが、「行き過ぎは是正される」という世の常にならえばそのうち起こることと言える。…暴落か徐々にかのそのスピードは知る由もないが。